2025年の百日咳流行は大人も警戒が必要です。
百日咳は、子どもの病気というイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし、近年は成人でも感染が増加しており、家庭や職場を通じて広がる事例が多数報告されています。
特に2025年は、過去最大規模の流行が確認され、大人の百日咳が社会的課題として注目されています。
大人の百日咳は初期の症状からは自ら気づくことが難しい感染症です。
そのため、咳が2週間以上続いても「風邪が長引いているだけ」と放置してしまう人も少なくありません。しかし、百日咳は強い感染力を持ち、乳児や高齢者に感染すると重症化のリスクが高まります。
この記事では、2025年の感染状況を踏まえつつ、大人の百日咳の症状・原因・治療法・予防法を詳しく解説します。

<本記事の監修>
林外科・内科クリニック
理事長
林 裕章 先生
<経歴>
1991年〜 佐賀大学医学部卒業、佐賀大学医学部一般・消化器外科入局、佐賀大学付属病院、佐賀県立病院好生館、祐愛会織田病院、多久市立病院等の研修を経て
2007年 医療法人林外科医院 理事長就任
1.2025年の感染状況|“かつてない規模”の大流行
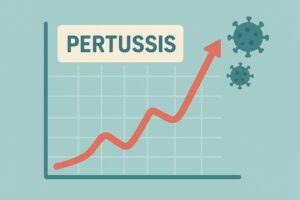
2025年は、日本国内で百日咳が過去に例を見ない規模で流行しています。
国立健康危機管理研究機構の感染症発生動向調査(IDWR)によると、第1~21週の時点で22,351例が報告され、前年の年間報告数(4,096例)の約5倍に達しました。さらに、8月末時点の累計は72,448例と報告され、年間を通じて過去最大規模の流行が進行中です。
また、沖縄県の報告によれば、第29週時点で累計918人が感染しており、前年(2024年)の86人を大幅に上回っています。
地域別では、新潟、東京、大阪など都市部に加え、宮崎や高知など地方都市でも人口10万人当たりの報告数が高い水準にあります。つまり、大都市圏に限らず全国的流行が進んでいる状況です。
さらに、懸念されるのが、マクロライド耐性百日咳菌(MRBP)の存在です。
MRBPとは、第一選択薬であるマクロライド系抗菌薬(クラリスロマイシン、アジスロマイシン、エリスロマイシンなど)に耐性を持つ百日咳菌のことです。
百日咳の治療には、マクロライド系抗菌薬が最も有効とされてきましたが、MRBPはこれらの薬が効きにくいため、治療が難しくなる点が大きな問題です。
2025年4月には乳児がMRBP感染により死亡する事例も報告され、治療の難しさが課題となっています。
<参照元>
IDWR「百日咳」2025年第22号(国立健康危機管理研究機構)
| 百日咳の予防におすすめのマスク
|
2.大人の百日咳とは?|基本情報と経過の特徴
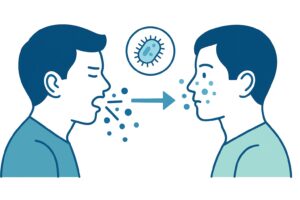
百日咳は、百日咳菌(Bordetella pertussis:ボルデテラ・パーテュシス)によって引き起こされる急性呼吸器感染症です。
感染経路は咳やくしゃみによる飛沫感染、あるいは患者の分泌物との接触感染です。
潜伏期間は7〜10日、長い場合は21日間に及びます。発症後は以下のような経過をたどります。

| 経過 | 期間 | 特徴 |
| カタル期
| 1〜2週間 | 風邪に似た症状(鼻水・軽い咳・微熱)。 診断が難しい時期。 |
| 痙咳期
| 2〜6週間 | 激しい咳発作を繰り返し、時に「ヒュー」という笛声様吸気音を伴う。 大人ではこの音が出ない場合も多い。 |
| 回復期
| 数週間〜数カ月 | 徐々に咳は軽快するが、完全に消えるまで長期間かかる。再悪化時は再受診を。 |
大人の場合、典型的な症状が出にくいため「長引く風邪」と誤解されやすく、診断が遅れるのが問題です。
<参照元>
3.大人の症状・合併症|意外と重い後遺症と感染リスク

大人の百日咳は、発熱が少なく長引く咳が中心という特徴があります。特に夜間に咳が悪化し、不眠や日常生活への支障が出やすいのが特徴です。
合併症や後遺症としては以下が報告されています。
(頻度の幅は多様な研究設定によるものです)。
| 合併症や後遺症 | 出現率 |
| 不眠 | 約77% |
| 体重減少 | 3〜33% |
| 尿失禁 | 3〜28% |
| 失神 | 2〜6% |
| 肋骨骨折 | 1〜4% |
| 無呼吸発作、副鼻腔炎、中耳炎、結膜出血 | 不明 |

咳による強い腹圧で肋骨骨折が起きるなど、軽い感染症では済まないリスクがあります。
特に骨密度が低下しがちな中高年以降、特に女性は注意が必要です。
また、稀に咳発作による胸郭への強い圧力変化で、目の血管に負担がかかり、結膜出血を起こすこともあります。
さらに、咳が続くことで、一時的に酸素供給が不十分になって失神に至るケースもあります。
このように百日咳は、大人にとっても生活の質(QOL)の低下というリスクがあるのです。
<参照元>
Pertussis: Microbiology, Disease, Treatment, and Prevention)
CDC「Chapter 16: Pertussis」)
4.大人が百日咳の社会への影響

いま、挙げたように大人が百日咳を発症すると後遺症で、長期間、仕事や家事に支障をきたす可能性があります。
加えて、職場・家庭への影響もあります。
また、軽症の場合でも大人は社会生活や家庭生活で多くの人と接触するため、百日咳に感染していることに気づかないまま仕事を続けたり、家族と過ごしたりすることで周囲へ感染を広げる危険があります。
特に小さな子どもや高齢者、基礎疾患がある家族がいる場合には命にかかわるリスクもあります。
このような理由から、大人の百日咳では予防と早期発見、早期受診が重要です。
5.診断と検査方法|早期発見が拡大防止の鍵
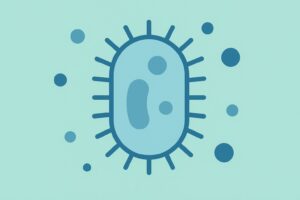
診断のポイント
|
1)診断の基本

百日咳の特徴的な臨床症状は「発作性の連続咳(whooping cough)」です。
特に夜間に悪化し、咳き込み後に「ヒュー」という笛のような吸気音を伴うことが多いです。
しかし、成人やワクチン既接種者の場合、次の理由で診断が難しいとされています。
| 典型症状が出にくい | 小児のような「笛声(whoop)」や激しい咳込みがなく、単なる長引く咳に見えることが多い。 |
| 他の咳症候群との鑑別が困難 | 感冒後咳嗽、喘息、アレルギー性咳嗽などと似た症状になる。 |
| 受診時期が遅れがち | 咳が2〜3週間以上続いて初めて受診することが多く、培養やPCRの陽性率が下がっている。 |
こうしたことから、臨床的には長引く咳(2週間以上)が診断のきっかけになります。
また、家族や学校、職場などで百日咳患者と接触があった場合は診断の可能性が高まります。
さらに、PT抗体(百日咳毒素抗体)の測定が診断の決め手になることが多いです。
2)検査方法
百日咳の診断は臨床所見だけでは難しいため、以下の検査が行われます。
①鼻咽頭ぬぐい液による培養検査
百日咳菌を直接分離培養する方法。
特異度は高い(陽性なら確定)が、菌が検出されるのは発症早期(2〜3週間以内)が中心。
感度は低めで陰性であっても否定はできません。
②PCR検査(遺伝子検査)

鼻咽頭ぬぐい液から百日咳菌のDNAを検出。
感度・特異度ともに高く、現在もっとも有用とされる方法。
発症から3〜4週間程度まで有効。
③血清抗体検査
血液中の百日咳菌に対する抗体(PT抗体など)を測定。
発症後2〜3週間以降に上昇するため、急性期と回復期のペア血清で比較するのが理想的ですが、実際には症状が出てから時間が経って受診されることが多く、その時点での抗体価を参考に診断します。
成人の長引く咳の診断で用いられることが多い。
なお、血清抗体検査は、下記のとおりワクチン接種後は、解釈に注意が必要です。
| 抗体価は百日咳に感染した時だけでなく「ワクチン接種によって上昇する抗体」があります。 そのようなワクチン接種後に抗体価が高い場合、「ワクチン接種したので抗体価が高い」のか「百日咳に感染している」のかが分かりません。 その点において、抗体価を測定する意義が低くなり、ワクチン接種後1年程度は抗体価を測定しないか、測定したとしても検査結果の「解釈に注意が必要」となります。 |
④白血球数の確認
特に小児では、リンパ球増多(白血球が2万/μL以上に上昇する)が見られることがあります。
単独では確定診断にはならないが、補助的に参考となります。
特に喘息やマイコプラズマ感染との鑑別が重要で、医師による的確な判断が求められます。
⑤画像検査(X線・CT)
肺炎やほかの疾患の除外診断のために行います。
百日咳の直接診断にはなりませんが、総合判断の材料として有効です。
<参照元>
3)日本の最新ガイドラインにおける百日咳検査の考え方
日本感染症学会や厚生労働省の指針では、以下のように整理されています。
| 確定診断 | 百日咳菌の分離培養陽性 PCR法陽性 急性期と回復期の抗体価上昇(4倍以上) → これらのいずれかで確定とされます。 |
| 臨床診断 | 典型的な発作性咳嗽が2週間以上持続 咳込み後の笛のような吸気音、または咳後嘔吐がある 百日咳患者との接触歴がある → 検査ができない場合や陰性であっても、これら条件を満たせば臨床診断が可能とされています。 |
| 推奨される検査の優先順位 | 発症初期(2週以内):培養・PCR 2週以降:PCR・抗体検査 3〜4週以降:抗体検査が中心
|
6.治療と感染拡大防止策|マスクの有効性も強調

1)大人の百日咳の治療
①抗菌薬治療
百日咳の治療の中心は抗菌薬です。
第一選択はマクロライド系抗菌薬(エリスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど)です。
発症から2〜3週間以内に投与すると菌の排出を抑え、周囲への感染を防ぐ効果が期待できます。
しかし、耐性菌(MRBP)の増加により、場合によってはST合剤(トリメトプリム・スルファメトキサゾール)やニューキノロン系抗菌薬(レボフロキサシンなど)が検討されます。
抗菌薬は「咳をすぐに止める」ものではなく、原因菌である百日咳菌の排菌期間短縮と周囲への伝播抑制目的です。
②対症療法
| 鎮咳薬 | 咳を抑える薬 ただし強い効果は期待しにくい |
| 去痰薬・吸入治療 | 痰や咳発作を和らげる補助的役割の薬 |
③日常生活でできること
十分な休養も咳で体力消耗しやすいため重要です。
また、次のような工夫で症状を和らげることが可能です。
|
2)感染防止対策

感染拡大を防ぐためには次の対策が有効です。
| マスク着用 | 飛沫拡散を防ぐ基本的手段であり、発症者本人だけでなく周囲の人の感染予防にも有効です。 感染が疑われる場合や診断を受けた場合は、必ずマスクを着用しましょう。 |
| 換気 | 閉鎖空間での菌の滞留を防ぎましょう。 |
| 家庭内隔離 | 可能な範囲で別室で過ごし、タオルや食器の共有を避けましょいう。 |
| 外出制限・職場や学校への配慮 | 抗菌薬を開始してから 5日間 は他人に感染させるリスクがあるため、登校・出勤を控えることが推奨されています。 学校保健安全法では「特有の咳が消失するまで」または「適正な抗菌薬5日間終了まで」出席停止です。 成人の出勤については法令の直接規定はありませんが、感染性は抗菌薬5日で大きく低下します。 また未治療では咳発症後3週間程度で感染性が低下すると言われています。 |
| 接触者への対応 | 家族や濃厚接触者には、マクロライド系抗菌薬による予防投与を検討することがあります。 |
| 消毒の実施 | ドアノブやテーブルなどをアルコール消毒液で拭き取ることで感染拡大を防ぐことができます。 |
| 百日咳の予防におすすめのマスク
|
7.予防法|ワクチン接種と日常的対策の強化

1)ワクチン
百日咳の予防はワクチン接種が最も有効な手段です。ワクチンはジフテリア・破傷風との混合ワクチンとして用いられています。
小児期「四種混合ワクチン(DPT-IPV:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)」が定期接種として行われています。
しかし、百日咳ワクチンによる免疫は5〜10年で減弱するため、中高生や成人では再感染のリスクが残ります。
それでも、日本では現状、定期的な追加接種はありません。
そのため、日本では 成人百日咳の増加や乳児への感染事例 が問題となっています。
今後、妊婦・医療従事者への接種や、学童期での追加接種が検討されています。
<参考:日本と欧米の百日咳のワクチン接種制度の違い>
| 対象年齢・層 | 日本の現状 | 海外(例:米国・欧州) |
| 乳児期 | 四種混合(DPT-IPV)を定期接種(計4回:生後3か月〜1歳半頃) | DTaPワクチンを定期接種(同様に4〜5回) |
| 学童期 (小中学生) | 定期接種なし | 11〜12歳でTdap追加接種(義務化や推奨が一般的) |
| 成人 | 定期接種制度なし(任意接種扱い) | 10年ごとの破傷風ブースターの際にTdapを接種推奨 |
| 妊婦 | 制度としての定期接種なし(推奨段階にとどまる) | 妊娠27〜36週にTdap接種を推奨。母体から胎児へ抗体移行し、新生児を保護 |
| 医療従事者 保育関係者 | 明確な接種指針なし | 接触リスクが高いためTdap接種を推奨 |
| 免疫持続期間 | ワクチン効果は約5〜10年で低下し、成人期には再感染のリスクあり | 同様だが追加接種により免疫を維持 |
成人の場合、日本では現状、定期的な追加接種はありませんが、任意接種(自費診療)として、三種混合ワクチン(DPT)や、海外で承認されている成人用の三種混合ワクチン(Tdap)を接種することが可能です。
特に、妊婦の方、乳児と接する機会の多いご家族、医療・保育関係者には、ご自身と赤ちゃんを守るために接種が推奨されています。
かかりつけ医やトラベルクリニックなどでご相談ください。
3)日常生活での予防
日常生活での予防としては以下が有効です。
| マスク着用 | 飛沫感染を防ぐ。 咳症状がある場合は必須。 |
| 手洗い・咳エチケット | 石けんによる手洗いと、咳を手で覆わずにティッシュや肘でカバー。 |
| 人混みの回避 | 流行期は特に注意。 |
<参照元>
<参考記事
【2025年最新】大人の百日咳予防対策|ワクチン・マスク・生活習慣まで徹底解説
https://aestheticmedicine.nahls.co.jp/infection/pertussis-prevention
百日咳の予防におすすめのマスク!選び方のポイントも紹介
https://aestheticmedicine.nahls.co.jp/infection/pertussis-mask/
8.大人の百日咳に関するよくある質問
Q1. 大人の百日咳は一度かかれば再感染しませんか?
大人が百日咳にかかると免疫を獲得しますが、数年で低下します。
そのため、百日咳に再感染する可能性があります。
Q2.妊娠中にかかるとどうなりますか?
妊娠中に百日咳にかかった場合、母体の重症化は少ないですが、新生児への感染リスクが高く注意が必要です。
Q3.市販薬で治せますか?
市販の咳止めは効果が限定的で、根本治療には抗菌薬が必要です。
Q4.百日咳の予防や感染防止対策にマスクはどの程度効果がありますか?
百日咳は主に飛沫感染(近距離咳しぶき)で広がるため、体調不良時の医療用サージカルマスクで排出源対策を徹底するのが基本です。
顔に密着し隙間が少ないことが特に重要です。
N95やJ95マスクの着用がより有効な場合もあります。
Q5.百日咳はどのくらいで咳は治まりますか?
百日咳は、その名の通り治療しても数週間〜数カ月続くことがあり、回復期は長引くこともあります。
9.まとめ|早期受診と予防の徹底がカギ
大人の百日咳は風邪と見分けにくく、診断が遅れがちです。しかし、2025年は過去最大規模の流行が報告されており、社会全体での予防意識が求められます。
そのため、予防はもちろん感染が疑われる場合は、早期受診が大切です。
咳が2週間以上続く場合は、呼吸器内科や感染症外来のある医療機関受診をしましょう。
また、大人の百日咳対策としては、マスクと咳エチケットで周囲への感染を防止することやワクチンによる予防も重要です。
大人の百日咳は風邪と見分けにくい感染症ですが、社会的に大きな影響を及ぼすため、正しい知識と予防行動が不可欠です。
自分を守るだけでなく、家族や社会を守るために、正しい知識と行動を実践しましょう。
| 免責事項 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の医学的アドバイスではありません。 症状がある場合や予防接種について詳しい相談が必要な場合は、必ず医療機関を受診し、医師にご相談ください。 また、ワクチンの接種可否や時期については、個人の健康状態や既往歴により判断が異なるため、専門医との相談が不可欠です。 |
SNS Share
\ この記事をシェアする /


